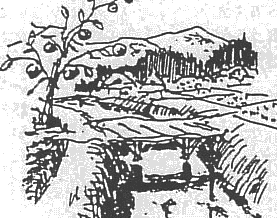| 旅の一座 |
| ■月刊「サムソン」1991.3月号〜12月号に連載(全10回) |
|
旅役者の唄 (作詞 西條八十 作曲 古賀政男)
秋の七草 色増すころよ
役者なりゃこそ 旅から旅へ
雲が流れる 今年も暮れる
風にさやさや 花すすき
時雨降る夜は 蟋蟀啼いて
なぜか淋しい 寄せ太鼓
下座の三味さえ 心に沁みる
男涙の 牡丹刷毛
幟はたはた 夕雲見れば
渡る雁 故郷は遠い
役者する身と 空飛ぶ鳥は
どこのいずくで 果てるやら |
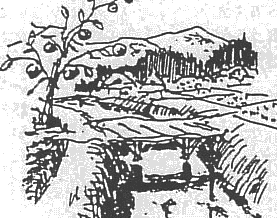 |
|
 |
| ■物語 |
| 昭和十二年、日華事変、昭和十三年、国家総動員法の発令、戦時体制が急速に強化されていく暗い時代背景の中で、男色というさらに重い荷を背負って生きる若者の旅を描く。 |
| ■あらすじ |
大正七年(1918年)、主人公・田村竹雄は飯塚から五、六キロ南西にある宝満山の麓の炭坑長屋で生まれた。両親は炭鉱夫だった。
昭和二年(1927年)小学校三年の春、祖父と関係を持つ近所の八百屋の親父=古城から、性器を愛撫され初めて快楽を知る。
以後六年間、竹雄は古城によって与えられる快楽の虜となり、高等科を卒業する頃には、亀頭は完全に剥け、古城の体を見ただけで、性器を勃起させ、古城に握られ舐められれば、即座に反応し、所構わず腰を振りたて多量の精液を撒き散らすまでになっていた。
昭和九年(1934年)高等科を卒業後、筑豊炭田の炭坑夫となり、十歳ほど年の離れた虎二を好きになる。
昭和十一年(1936年)八月、盆踊りの夜、憧れていた虎二と結ばれる。しかし九月、古城が開いた虎二の恋人清次の出征の為の送別会で、古城と旅役者徳助の男色行為を見て、竹雄は今度は徳助に一目惚れする。そしてその夜、古城の性器を初めて体に挿入され、若い虎二にない熟年の男色者の男としての体に圧倒的に魅了され、初めて自分の性の対象を知る。以来、虎二を避け、古城に抱かれるようになる。
昭和十二年(1937年)正月、竹雄は古城に逢いに来た旅役者・徳助に抱かれた後、「轟竜太郎一座」に入るよう薦められ、旅の一座に入ることを決心する。
座長への恋慕、その恋人新五(59)への嫉妬、他の座員たちに隠れて行う徳助(65)との刹那的な交合。
座員の世話係として、旅に加わった竹雄は、やがて炊事係となる。
柳川の楽隠居・伝三(69)、八代の巨根の漁師・金十(40過ぎ)、阿久根の浄光和尚(53)、ボーと呼ばれる番僧と鹿児島の狐狸庵に住む慈空和尚(75)。都城の彫り師・駒蔵(60)と下男・常吉(70)、行く先々で出会う男色者たち。
様々な出会いと別れを繰り返し、竹雄は次第にウケからタチに変わっていく。
昭和十三年(1938年)三月、徴兵検査の知らせが十九歳の竹雄の元に届く。検査を受ける為、帰郷する竹雄は、道すがら慈空和尚、浄光和尚を訪ねる。
|
| ■ちょっとだけよ |
旅の一座 第一回
|
| 〔四〕轟竜太郎一座 |
英彦山の山地に源を発する遠賀川が、福岡県北部の芦屋で玄界灘に注いでいるが、飯塚はどちらかといえば遠賀川の川上に広がった街である。そして現在でもそうであるが、飯塚駅を背にして右側に二百メートルも歩き、遠賀川の橋を渡れば、地方都市にしては珍しく大きな飯塚劇場がある。
石炭産業が俄に活況を呈しはじめた明治の終わりに、住民の要望によって建造された本式の劇場だった。広くとった前庭にはやぐら太鼓が設置され、入り口には観客の下駄を預かる場所があり。回り舞台も設置された九州でも有名な劇場だった。
筑豊炭田の中心地で、炭鉱で働く多くの坑夫たちは街を練り歩くちんどん屋の鐘の音や、やぐら太鼓の音を聞くと早めに夕食をとり、一日中の汗を流したあと芝居を見るため飯塚劇場に駆けつけた。外題は『滝の白糸』『名物赤城山』『瞼の母』等だったが、それを見る善男善女たちは、泣いたり笑ったりしながら、一日のストレスを吐き出した。
やぐら太鼓が鳴り響き、劇場の前面に立てた多くの幟が風にはためく飯塚劇場では連日満員の盛況で、坑夫たちは、芝居の外題について、『次の外題は何だろう』というようなことを楽しそうに話しあった。と同時に芝居をする役者についても、それぞれに贔屓があり坑内の昼休みでは、○〇一座のどの役者がいいというような話で持ちきりだった。
竹雄は幼いときから何度も、両親に連れられて芝居を見物に来ていたので、一座の名前や彼等が一週間か十日すると、何処かの街に移動するというようなことも、おぼろげながら知っていた。しかし彼が自分の意志で見物にくるようになったのは、轟徳助を知ってからだった。
徳助は轟竜太郎一座の名脇役だった。そして座長の轟竜太郎は当時五十歳前後の端正な役者で、百六十五センチ、七十キロの標準よりいくらか肥満した男だった。最盛期には二十五、六人もの座員を抱えていたが、最近十五人に減らしていた。特別綺麗な女を二人と可愛い女を二人、それに徳助のような何でもこなす名脇役がいれば、後は少しだけ個性の強い役者を三、四人に、舞台に出ただけで観客を笑わせることのできる役者を一人と、歌の上手な役者を揃えていればよかった。
轟竜太郎は端正な顔に理性が滲み出たような容貌で、外題は一般的な人情物の中に必ず文芸物を一つ入れるような役者だった。例えば島崎藤村の『夜明け前』や谷崎潤一郎の『春琴抄』などをさりげなく人情物の中に入れるというやり方だった。そのため暇さえあると演劇の勉強を欠かさなかった。
その助言をしたり、新しい外題を考え座長に提言するのが轟新五という六十歳近い小太りの男だった。どちらかといえば大所帯に属する轟竜太郎一座は、そういう陣容で時には文芸物を公演するということで、文化に飢えていた当時の筑豊炭田ではユニークな一座として結構ファンが多かった。
楽屋雀の話によると座長の轟竜太郎は、若いとき一度だけ結婚しているという。楽屋雀というのは芝居通のことで何時も楽屋に出入りして、芝居や役者の消息に詳しい人のことを言うのだが、竜太郎は一座の中で最も綺麗な、轟花奴を妻がわりに愛しているというようなことも、誠しやかに語られていた。
そんな一方では、竜太郎は相談役の轟新五とは、男同士の夫婦だというようなことも流されていた。当時の善男善女たちは、男同士の夫婦という意味は理解出来なかったが、たぶんそうだろうというような噂は、流されればそのまま人気に繋がった。
そして彼の十八番は、『瞼の母』の忠太郎役や、『名月赤城山』の国定忠治役だった。ごくありふれた外題であり、どんな人の心にも素直に入って涙を絞らせる芝居だったが、こういう芝居にこそ座長の知性が必要だと、竜太郎はかたくなに信じ、努めて人間の心の深みをだそうとした。ありふれた軽い芝居に知性が加わると、観客の表情が変わった。
木枯らしが何度か吹いて年が改まった。竹雄は殆ど毎晩のように古城に抱かれて、男色の手ほどきを受けるとともに、芝居の話に耳を傾けた。芝居の話は大抵の場合、古城の性器を肛門の奥深くに受けて聞くことが多かった。挿入したままじっと静止していることもあったし、抽送を繰り返しながら話すこともあった。
「座長の竜太郎さんは、れっきとした男色者で、三拍子揃うたよか男たい」
古城の話はこんな風にして始められる。
『三拍子とは何のことね』と竹雄が訊ねるのを待ってから、今度はその三拍子についてわかりやすく丁寧に説明する。
「三拍子揃っていいというのは、顔がよくて、性格がよくて、しかも体がよかことじゃ」
そして、体がいいと言うときに、彼の手が竹雄の性器に棒握りする。
「もっとわかり易く言えば、竜太郎さんのごと男振りがようて、おとなしく素直で、しかも体が綺麗で大きなマラをぶらさげとる男のことをそう言うのじゃ」
古城の亀頭が竹雄の直腸を、微妙な動きで掻き混ぜ、竹雄は思わず声を上げた。
「それに竜太郎さんの嫁さんは、轟新五という六十歳の役者じゃ。新五は百六十五センチの身長にたいして七十五キロの体重があり、可愛い顔をしとるので、時には竜太郎さんの代役をこなす時もある。ばってん新五は毎晩、竜太郎さんの太かマラを尻の穴に受けて、どろりとした精液を体の中に吸収しとる」
「そんなら徳助さんは、何んばするとね」
竹雄はさしあたって最も聞きたいことを訊ねた。勃起した古城の亀頭が竹雄の直腸を摩擦するので、体の隅々にまで行きわたる快感のため自然に口が開いてくる。
「ああっ、徳助はただの男色者じゃ。それも若いときはタチで誰の尻にも入れとったが、六十五、六歳ころからウケになってしもうた。今じゃあ俺のマラを受けて、よう泣くようになった。ばってんおまえを抱くときは、たぶん完全なタチになれるはずじゃ。こんど竜太郎一座が飯塚にきたら、俺が話をつけるけん徳助に抱いて貰え。いいか」
古城はそんなことをゆっくり話ながら、次第に欲情の度合いを増し、最後はもっと卑猥なことを口走りながら、竹雄の肛門の中にどくどくと射精をするのが常だった。そして射精後の後始末を竹雄にさせながら語りかける言葉も決まっていた。
「おまえこんなところにいるより、少しでも早く満州にでも行って一旗上げてこい」
一旗あげるとは当時の流行言葉で、内地ではうだつのあがらない男にたいして、満州にでも行って、しこたま金儲けしてこいとでもいうような意味である。
そして再び轟竜太郎一座が、飯塚劇場に公演にきたのは高宮八幡宮の桜がちらほら咲きはじめたころだった。
◇ ◇ ◇
朝からちんどん屋が太鼓や笛を鳴らしながら飯塚の街々を練り歩いた。『轟竜太郎一座が再び飯塚に帰って参りました。この度は文芸大作品、室生犀生作の『あにいもうと』を上演いたします。座員一同が一生懸命に勤めますので、お揃いでお出かけください』というような口上を述べる。何十もの幟がはたはたと春風にはためき、やぐら太鼓が激しく鳴り響くと飯塚の芝居好きな人たちは、とたんに落ち着きをなくしてしまう。
徳助が古城さんの家に来たのは真夜中前だった。夜の芝居がはねてすぐ来ても、そんな時間になってしまう。彼は部屋の中に入るとすぐ古城の着物の裾に頭を突っ込んだ。その頭が上下に動き始めた。
徳助の下半身は畳に伏せているのだが、竹雄の目を意識して既に完全な男になっていた。それはその夜が古城のために来たのではなく、竹雄をタチとして抱くために来たという自覚の故だった。着物の裾が割れて腹に添って勃起した陰茎が見えた。
それだけで竹雄の肛門がひくひくと収縮を繰り返した。過去にはどんな男を見てもそれほどにはならなかった。六ケ月前に襖の隙間から見た徳助は、古城に後から犯されて泣いていた。帰り際に見たその人の人品や体にすっかり惚れ、一度は抱いてもらいたいと古城に執拗に頼んだ上での出会いだった。
徳助は古城の性器を口から離すと、竹雄のほうに向いて自分の体をみせた。ひどく太ってはいないが、適度に肉がついており、ぬめるような肌だった。七十歳という年令が信じられなかった。殆ど白くなった陰毛の中から形のいい性器が完全に勃起して、ターゲットを竹雄に向けている。
竹雄は躊躇わずに徳助の勃起を口に含んだ。扱い馴れている古城のものとは又違った味だった。こちこちに固くはないのだが、ぼってり膨れたまま長く伸びているに違いないと思えるような固さだった。何時の間にか徳助の指が二本とも竹雄の肛門の中にぴったり入っており、それは静かに直腸の中を掻き回している。それだけで竹雄は精液が弾けそうだった。
竹雄はあまりの気持ちよさに、じっと目を瞑った。目を開けて徳助の端正な顔を見たいと思うのだが、何故か目が開けられなかった。
「よしよし、よしよし」と徳助が赤ん坊をあやすような声でをだした。それだけで、竹雄は夥しい量の精液を吐きだした。
「どうじゃ、竹雄の都合のいいときに、轟一座に入らないか。おまえならできる」
徳助がそう言った。目の前が急に明るくなるような気がした。今まで必死で捜していたものの正体を掴んだ彼は、返事の代わりに、ひしと徳助の体にしがみついた。
「旅の一座は淋しいけれど、時には楽しいこともあるぞ。一座に入れ、竹雄……」
徳助が再び、そう言った。
(続く)
|
|