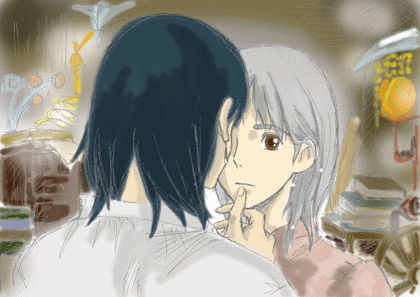 |
続・小さな邪マモノ −1− |
| 「んー………」 夕飯も終わり、銀色の月が空高く上る頃。 ソフィーは風呂場の鏡に映る自分を、ジッと覗き込んでいた。 洗い立ての銀色の髪。 水滴る、お風呂上りでほんのり赤みがかった肌。 そして、顔。 ソフィーは、その顔のパーツの一部である唇を右の人差し指でひと撫でした。 そして眉根を寄せてみせる。 「うぅ〜〜……」 そこは、風呂から上がったばかりだというのにカサカサしていて。 おまけに、少し切れているところもあって痛い。 ソフィーは、そんな乾燥した唇を見ながらちょっと考える。 考えて。 湯気で少し曇ってしまった鏡を手の平で撫でて。 うん、と鏡に映る自分に微笑んで見せた。 「ハウルなら、何か唇に塗るいい薬とか作ってくれそうね」 そう言いつつ、ソフィーは棚の上に置いてあったバスタオルを手に取った。 * * * 「口に塗る薬?」 そんなハウルの言葉に、ソフィーは頷いてみせた。 ここは城の二階にある、ハウルの部屋である。 そこは、相変わらずといっていいほど派手な飾りで埋め尽くされていて。 しかし、ソフィーが嫌がるハウルを横目にいくら片付けをしたところで、この部屋だけは毎日どことなく散らかってしまうのだ。 そんな、今は見慣れたハウルの部屋。 そこの一角にあるベッドの上で、ハウルは本を読む手を中断してソフィーの方を振り向いた。 「うん、荒れてしまって痛いの。何かいい薬とかまじないとかないかしら」 ソフィーはそう言いつつ、困ったような表情を浮かべてみせた。 するとハウルは、そんなソフィーに視線を向けたままベッドから降りて。 近づく。 「……ふぅん」 かと思うと、ハウルがそう呟きながらソフィーの唇を指で撫でてみせた。 |
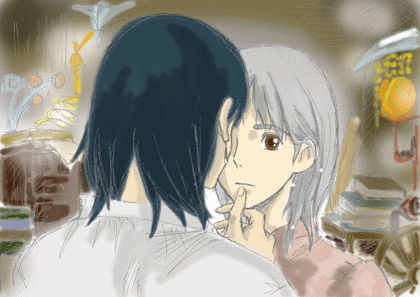 |
|
………確かに、荒れてる。 ハウルは、撫でた指から感じる柔らかい感触に混じって、所々カサカサした所があることに気がついた。 これだけ乾燥しているところを見れば、ソフィーはきっと痛かったに違いない。 それならば、と。 「いいまじないならあるよ、ソフィー」 「本当?」 そんなハウルの言葉に、ソフィーは嬉しそうに聞き返して。 よかった、と微笑む。 そんな屈託ない笑顔を見せるソフィーに、ハウルは優しく目を細めて。 唇に置かれたままの自分の指を、そっと頬へと移動させた。 頬に置いた手に触れる、ソフィーの髪。 洗ったばかりでまだ乾ききっていないのだろう、いつもの様な軽さはなくて。 でも、柔らかい。 「じゃあ、まじないをかけるから目を閉じて」 「目?う………っん」 途端。 ソフィーが言葉にしようとした「うん」は、何故かぎこちないものとなり。 一瞬、なにかに空気を呑まれたかのような錯覚に陥る。 頬に触れる、手。 近くで感じる、体温。 重ねられた、唇。 ソフィーは、気づいた時にはすでに、ハウルに言葉ごと呑みこまれていたのだった。 |