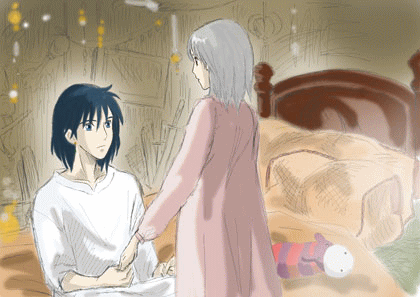 |
続・小さな邪マモノ −2− |
| 「う……っん」 突然のハウルの行動に驚いたのはソフィーである。 頬に触れる、手。 唇に感じる、感触。 思わず、閉じていた目を勢いよく開けた。 そこは―――――――――暗闇。 ソフィーは、一瞬そんな感覚にとらわれた。 しかし。 落ち着いて、よく考える。 一、二度瞬きをして。 そう。違う。 暗闇なんかじゃなくって。 暗闇と感じるほどの至近距離に――――――――ハウルの顔があるのだ。 「ハ……っハウル!」 ソフィーはそのことを頭で理解すると、恥ずかしさも手伝ってか、どうしたらいいのか分からずに両手でハウルを押し退けた。 するとハウルは、以外とすんなりソフィーから離れた。 かと思うと、そのままベッドに腰掛ける。 そして、さらりと言う。 「嫌だった?」 「!!」 それは、完璧とも言えるほどのソフィーの心理状況を掴んだ言葉で。 ソフィーは言葉に詰まったまま、口をパクパクさせてみせた。 そう。 嫌じゃない。 嫌なわけないのだ。 だって目の前にいるのはハウル。 誰よりも大好きなハウルなのだから。 でも。 ソフィーは、足元へ視線を落とした。 ゆっくりと、息を吸う。 そう。一応ソフィーだって、恥じらいもつ乙女である。 しかも恋愛経験が乏しいぶん、それに関しての表現が下手で。 自分で言うのもなんだが、愛だの恋だのに関しては、右も左も手探り状態の初心者そのものなのだ。 そんな自分に。 そんないっぱいいっぱいの自分に。 ハウルは。 「嫌だった?」 と、聞いてきたのだ。 当然ソフィーの頭の中は、一瞬で真っ白になる。 嫌なわけ、ないけど。 嫌じゃないよなんて、なんとなく照れくさくて言えない。 でも言わないと勘違いされそうで。 ハウルがいじけてしまいそうで。 もう、こんな自分が嫌〜〜〜〜っ!! すると、そんなソフィーの胸中を察したのか、ハウルが喋れなくなっているソフィーの代わりと言わんばかりに口を開いた。 「この間はヒンに邪魔されたからね。でも今日は誰も邪魔者がいない」 そして、微笑む。 まるで、ソフィーにガチガチに固まった緊張をほぐしてくれるかのように。 「あの日僕は、夜通しでソフィーを待ってたんだ。なのにソフィーときたら、いつまでたっても来る気配はない。あの時は、一人で朝を迎えながら、僕は本気で闇の精霊を呼び出すところだったよ」 そんなハウルの言葉に、ソフィーは思わず彼を見据えた。 一度目は女の子にふられて。 二度目は、オレンジに染まった髪の色。 そして三度目は、ソフィーに拒まれたから? そこまで考えて、ソフィーはぷっと小さく吹き出した。 そして、そのままクスクスと小さく笑い出す。 そう、結局は。 ハウルは純粋で真っ直ぐな人。 まだまだ知ってるようで、何もしらない弱い人。 自分と―――――――――同じなのよ。 途端、自分の中にあった「緊張」の二文字が不思議と和らいでいくのを感じた。 ソフィーは小さく笑っている自分を見て、少々不満げな表情を見せているハウルへと近づいた。 そして、嬉しそうに微笑む。 「……ハウル」 二人、手をのばせば届く距離。 ハウルが、青の双眸にソフィーを映しつつ目を細める。 そして、そのまま両手でソフィーの手を優しく包み込んだ。 |
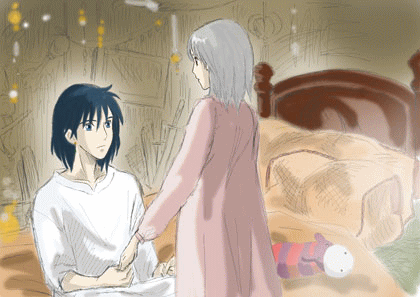 |
| 「大好きだよ、ソフィー。僕の大切な……奥さん」 「………うん」 そして、ハウルはソフィーの両手を引き寄せた。 必然的に、ソフィーはハウルの身体に倒れこむ形になる。 お互いの体温を、お互いで感じあって。 目を閉じる。 そして―――――――――もう一度静かにキスをした。 今夜は、ヒンもマルクルもすでに寝ていて。 荒地の魔女ことおばあちゃんも、すでに夢の世界。 カルシファーは、滅多に暖炉から動かない。 そう。 二人にとっての邪魔物は、誰もいないのだ。 強いて言うならば、現れないことを願うべきだろうか。 そんなことを考えつつも―――――――――長い夜は、ふける。 |