| 身の程を自覚し幸運を拓いた女性 |
〜 明石の君 ・ 明石一族 〜  |
〜 明石の君 〜 朧月夜との事件で、華やかな宮中から、暗転の須磨へと、源氏は自ら都落ちを決意し ます。 (源氏25歳) 播磨守・明石入道の誘いにより、須磨から 明石の浦へと移り住むことになり、都にも 劣らぬ風情と心遣いに落ち着いた日々がはじまります。 我が娘を都人に縁づけようとする父の期待に応えるため、明石一族の身分の低さに心 を痛めながらも、娘(明石の君)は源氏にひかれていきます。源氏も入道の希望どおり 娘を受け入れます。 歳があけ、源氏の赦免が決まります。懐妊した明石の君を残して帰京し、権大納言に 昇進します。2年ぶりに帝と対面し宮中へ復帰を果たしたのです。(源氏27歳〜28歳) 源氏が帰京した後、明石の君は女子を出産しますが、紫の上の養女として2歳の幼子 は都へ引き取られます。10年後、明石姫君は天皇家に嫁して、男子(匂宮)を出産し ます。明石の君は、姫君の実母として後見役となり、明石一族を再興させたのです。 明石の田舎で育った身分の低い女性が、苦労の末に最後につかみ取った幸せとは、 下積みの愛と、謙虚さ。それから「身分社会」で 身の程を自覚したことだと思います。 |
〜 王朝の雅 〜 お香 六条院  21巻少女より 21巻少女より今日の講座は、お香を聞きながら “王朝の雅” の世界へ! ◎ 六条院 源氏35歳の秋に落成。 ○ 春のお屋敷 → 紫の上(正妻)・・源氏の住まい。 ○ 秋のお屋敷 → 秋好中宮 (六条御息所の娘) ○ 冬のお屋敷 → 明石の君 ○ 夏のお屋敷 → 花散里 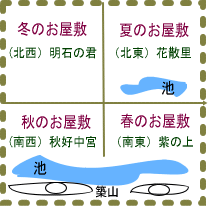 ・六条院は、4町で、84丈 (約 252メートル)四方。 ・1町は、東京ドーム約1個分といいますので、六条院全体は、ドーム4個分。 ・屋敷の規模からみて、この時代の「上流貴族」の栄華がうかがえます ◎ 薫物合 (たきものあわせ) ・・・ 薫物の匂いの優劣を競い合うこと。 ・自分たちで調合してお香を作り、お嫁入りに持たせるといいます。 ・日本の温暖な気候では香材が育たず、中国経由でインドから取り寄せたとい います。 お香は高価な貴重品でした。 当時の遊びのひとつです。 ○ 歌合 (うたあわせ) ○ 花合 (はなあわせ) ○ 根合 (端午の節句の折、菖蒲の根の長短を競うもの) ◎ 衣配り (きぬくばり) ・六条院でのお正月用に、女君達の装束を整えて源氏が方々に贈ります 十二単  トップへ 源氏物語の女性 理想的な女性へ |