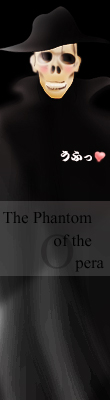□ Don Juan Triumphant □
業火に焼かれた無残な姿・・・
醜く歪んだこの顔・・・
ファントムはどんな顔をしていた?
・・・――――――――――――・・・――――――――――――・・・何かにつけ「醜い」ことが強調されているファントムの顔ですが(おいたわしや・・・)、では実際彼はどんな顔をしていたのだろう。
一応ガストン・ルルーの原作をベースとしながらも、舞台と原作、スーザン・ケイの『ファントム』と原作の間には、微妙な違いがみられる。
まずは舞台から。
アンドリュー・ロイド=ウェバー版の舞台では、顔の右半分が大きくひきつり、髪の毛は白髪でまばら、頭に大きな傷があるビジュアルとなっていますね。
普段のファントムは、カツラと顔の右半分を覆う仮面で、醜い傷を隠している。
原作およびスーザン・ケイの『ファントム』では、”鼻がない”ことが、ファントムの容貌の大きな特徴として取り上げられているのですが、鼻なしメイクの実現が難しかったのか、それとも見た目に不気味になりすぎるので避けたのかは分かりませんが、舞台では採用されていません。ないものを付け足すのは比較的簡単ですが、あるものをないように見せるのは意外と難しいので、その辺も理由の一つなのかな。
舞台でのファントムの顔の描写に関して特徴的なのは、ファントムの顔の醜さが先天的なものか、後天的なものかを曖昧にしている点です。
「業火に焼かれた無残な姿になろうと・・・」というファントムの歌、またクリスティーヌの「無残に焼け爛れて、ひきつっている恐ろしいあの顔」という歌詞からは、何らかの事故によって後天的に傷を受けた可能性も見いだせる。
しかし一方でマダム・ジリーとラウルの会話の中では、先天的なものであると結論付けられているし、最後に歌われるファントムの「血に呪われた運命」という歌詞もまた、血に呪われる=生まれながらの顔の醜さ、をそれとなく示唆していますね。
舞台上でははっきりとした結論は出していませんし、どちらで理解しても間違いではないと思いますが、個人的にはやはりファントムは先天的に醜い顔を持って生まれて来たのではないかと思いますね。
何らかの不幸によって後から傷ついたのではなく、誕生という極めて無防備で根源的な時から、彼は「普通」という輪の中からはじき出されてしまった。
「己の存在を誰からも祝福されなかった、誕生時においてさえも・・・」という、自己の存在に対する拭いきれない不信感は、ファントムの人格形成を考える上で大きなポイントになると思います。
時に崩れ落ちそうになる人間として存在意義。
自分は何のために存在しているのか、存在する価値などあるのか?という疑問を、恵まれた才能でなんとか打ち消しながら生きてきたのでしょう。
お次はガストン・ルルーの原作について。
原作の中のエリックの容貌に関する描写を抜き出してみると・・・「ものすごくやせた、骸骨みたいな骨格をしていて、黒い服がだぶだぶだったよ。目はすごく奥に引っ込んでいるから、じっと動かない瞳もよく見分けられないほどだ。要するに、どくろみたいに二つの黒い大きな穴しか見えないんだよ。皮膚は太鼓の皮みたいに骨の上にぴんと張られていて、白いどころか、気味が悪いほど黄ばんでいる。鼻ときたらないも同然で、横からでは見えないほどだ。それに鼻がないってのは、見てぞっとするものだよ。額の上や耳の後ろの三、四本の長い毛は、頭髪の代わりをしてたな」
「眉根がひどくくぼんで黒い穴のようになった、とても青白く陰気で醜い顔」
「その姿は見る人の心をたちまちにしてこの上もなく暗い気分にした」
「死体のように青白く痩せた男」
「何世紀にもわたって乾燥されてきたどくろ」
「真暗闇でなければ彼の燃えるような目は見えない」
「唇のない歯でぞっとするきしみ音をたてながら」
「わたしがすっかり死で作られているのを知るんだ!」
「彼はあの恐ろしい鼻の穴のあるところに、口髭のついた混凝紙の鼻をつけていた。それでも彼の醸し出す不吉な感じは完全には取り除かれなかった」
(創元推理文庫『オペラ座の怪人』三輪秀彦訳より引用)
うううぅむ。ひどい書かれようだ(笑)
絵にすると左の絵のような感じですかね。
歴代の『オペラ座の怪人』の中では、ロン・チャニー扮するエリックが、最も原作に忠実な外見をしていると言えるのかな。
しかし、実際には唇がないと歯の隙間から息が漏れてしまうので、天使のような声で歌を歌うのは難しいでしょうねぇ。鼻孔に声を響かせられないのも辛い。
(絵を描きながら、「どくろ顔でも、笑うと結構可愛いんでないかい?」と思ってしまった私は、どこか間違っているのだろうか・・・)
原作においては、エリックの容貌は完全に先天的なものとして描かれています。
外見の醜さもさることながら、もう一つ、彼には見る者に「死」を連想させる雰囲気があったようですね。もちろんどくろに似た外見も「死」を連想させる大きな要因だとは思われますが、クリスティーヌはエリックの素顔を見る前の段階で、彼の骨ばったすらりとした手に「死の匂い」を感じていた。
彼は存在の中に、死を感じさせる独特の気配のようなものを含んでいたようです。
最後にスーザン・ケイの『ファントム』。
「一面に青い血管が浮き出た、薄く透き通った皮膚の下からは、頭蓋骨がすっかり見えてしまう。落ち窪んだ目は左右不釣り合いで、口は原型をとどめず、鼻があるべき所には恐ろしい穴がぽっかり口をあけている」
「その子はとうの昔に死んだ人のような様子をしていたのだ」
「”自然の手違い” ”化け物のようなお荷物”」
「仮面の陰で、血が出るほど唇を噛み締めた」
「全てが違っていながら―何ひとつ変わりがない」
「今にあなたもそっくりになる―死んで何ヶ月かしたらね!」
「鼻がないってのも、便利なところもあるんだよ」
(扶桑社ミステリー『ファントム』北條元子訳より引用)
『ファントム』を読むたびに思っていたのですが、スーザン・ケイのエリックに対する描写は、いつもどこかしら肉感的ですね(笑)
基本的には原作に沿った容貌を採用しているにも関わらず、原作の描写にある乾いた感じはなく、文章の中に湿気た肉の匂いをただよわせている。
乾燥した骸骨ではなく、生きた肉の塊であると。
原作と多少異なる点としては、スーザン・ケイのエリックには唇があったようです。
舞台のファントムが持っている暗く妖しい情熱の輝きと、原作のエリックが持っている死を思わせる陰気なかび臭さの、ちょうど中間地点(やや舞台寄り)に位置するエリックかなと。
色々な価値観が飛び交う情報化の進んだ現代においては、エリックの顔はそれほど忌避されるべきものではなくなっているのかも知れません。
世の中の人間が、自分の想像を越えて多様であることを私たちは知っている。
顔を出さなくても才能さえあれば、それなりに活躍できる時代になりましたしね(笑)
ではもう、時代遅れの話なのか?
いえいえ。
どこかで何かが人より劣っているのではないか・・・という思いは、程度の差こそあれ時代を超えて小さなエリックとして誰の心の中にも存在します。
その不安感ゆえに人を見下し、見下すことで自分は意味のある存在なのだと安心しようとする心の動きもまた、誰の中にも潜んでいるものです。
顔の造作に関してもそうですが、勉強ができない、スポーツができない、気が利かない、劣等感をかきたてる火種などそこら中に転がっている。
自分なりに受け入れたつもりでも、他人の何気ない仕草の中に、自分への無意識の評価を見いだす時、何とも言えない苦い思いが込み上げてくる。
エリックが何度も噛み締めたであろう、苦い思い。
そういう意味では、極めて特殊な状況を描いているように思えるこの『オペラ座の怪人』の物語も、実はごく日常的な心の動きを拡大して描いているに過ぎないのかも知れません。
← Back