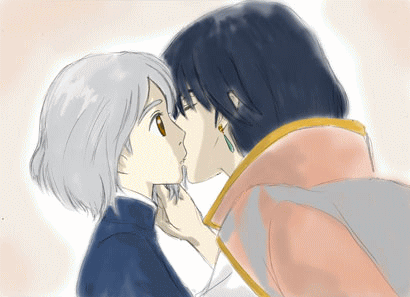 |
時間の呪文 −10− |
| 結局。 あれからソフィーが気持ちを落ち着かせるまでに、ずいぶんな時間がかかってしまい。 ようやくハウルにルーイのことを聞くことが出来たのは、太陽がとうに高く昇りきったころだった。 「……………」 しかし。 そんなソフィーの質問に対して、何故かハウルはなかなか口を開こうとはせず。 暖炉の前。 ハウルが椅子に座って、ソフィーがハウルの前に立って。 二人向き合ったまま――――――――少しの沈黙が流れる。 そして、そんな沈黙が耐えられなかったかのように、まず口を開いたのはソフィーだった。 ハウルに一歩、近づいて。 「ねぇ、ハウル。ルーイがどういう呪いにかかっているのか知っているのでしょう?教えて」 そんなソフィーの言葉を横で聞いていたカルシファーが、チラリとハウルの方へと視線を動かした。 ぱちぱちとカルシファーの火の粉が淡く部屋を照らす。 しかし。 そんなソフィーの質問に、やっぱりハウルは答えようとはせずに。 代わりに自分の首にかけてあったネックレスの飾りを持ち上げて、手の内で動かしてみせる。 それは、光に反射してキラキラと輝き。 かと思うと、飾りから手を離し、何が気にくわないのだろうか少々不機嫌そうな顔をソフィーに向けてきた。 「………そんなにルーイのことが気になる?」 「へ?」 ようやくハウルが口を開いてくれたかと思ったら、あまりにも予想外な言葉が返ってきたため、ソフィーは思わず間抜けな声をあげてしまった。 見るとハウルは、真剣にソフィーの方を見ていて。 真剣に、ソフィーの返事を待っていて。 気まずいほどの、この空気。 「……………」 ソフィーは、思わず息を呑んでみせた。 横でカルシファーが、ニヤニヤしているのが痛いくらい分かる。 そう。ハウルってば。 もしかして。 ううん、もしかしなくても。 絶対に。 ルーイにやきもち―――――――やいてる?? なっ、なんで〜〜〜〜〜〜っ!! ソフィーは思わず胸中で悲鳴をあげてみせた。 ハウルのやきもちは、正直嬉しい。 私のことを好きでいてくれる、想ってくれている証拠。 しかし。 今回は、違うのだ。 ソフィーは、いったん頭の中をどうにか整理しようと努力した。 そして、いまだニヤニヤしているだろうカルシファーに軽く視線を向けて、それを制し。 ふぅ、と深く息をつく。 そう。 今回ばかりは、違うのだ。 ルーイのことが好きとか。 気になるとか。 そんなんじゃない。 そんなんじゃなくて、私はただ――――――――― と、ソフィーはここまで考えて、何故かゆっくりと顔を伏せた。 考えれば考えるほど、ぐちゃぐちゃになってきて。 その考えをハウルに言ったところで、墓穴を掘ってしまいそうで。 でも、ハウルには分かってほしくて。 「……………」 するとハウルは、そんなソフィーを見て少しの間を置いてから、小さく溜息をついた。 そして重そうに、はたから見ればしぶしぶと口を開く。 「………ルーイにかかっているのは、呪いとかそんな簡単な類のものじゃないよ。もっと大きな……」 「え?」 まさかハウルが答えてくれるなんて思ってもみなかったソフィーは、思わず顔を上げた。 かと思うと、ハウルは椅子を立って机の上に置いてあった派手な上着に手をかける。 「……いや、何でもない。それよりちょっと出かけてくるよ」 「ハウル!」 ソフィーは、そんなハウルに駆け寄って。 するとハウルは、上着を着ながらソフィーの方へと振り向いた。 そして、ゆっくりと言葉を紡ぎ始めた。 まるで、一つ一つを言い聞かせるかのように。 「……ソフィー、君は魔法や呪文というものを、まだ知らなさすぎるんだ。魔法は確かに便利だし、使い方によっては人ひとりの運命だって大きく変えてしまう事だって出来る」 いつしか太陽には雲がかかったのだろう、窓からさす日の光が陰り。 カタカタと小さく窓が鳴る。 「でも、逆に言えばそれだけ代償も大きい」 ハウルが何を言っているのか分からずに、ソフィーは小さく首をかしげてみせた。 どこか、不安げに。 そして、そんなソフィーを見ながらハウルは少しだけ声のトーンを落として。 「………使い方を間違えれば、最悪の結果が待ってるってことさ」 そんなハウルの言葉に、ソフィーはハウルの上着を右手で心もとなく掴んで。 ハウルを、見上げる。 「何、どういうこと?分からないわ、ハウル」 そんなソフィーに、ハウルはそっと銀色の髪に手をのばした。 ふわり、と柔らかい感触が手に伝わって。 「……あまり深入りするなってことだよ。ルーイのことはルーイ自身にしか分からないんだ」 そして、そのまま髪を梳き。 ソフィーに軽く、口づけをした。 |
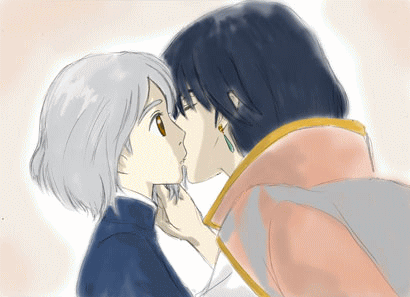 |
そのまま空いた両手で、ソフィーの手を優しく包みこんで。 目を閉じる。 暖かな感触が、お互いの唇に伝わり。 それを名残惜しむように、ハウルはもう一度キスをして。 扉へと、向かった。 背後には真っ赤な顔をしたソフィーが立っているのだろう、ハウルは取手の色を黒に変えた。 そして、重い音を立てて扉を開ける。 吸い込まれるような陰圧の空気を肌に感じながら、ハウルは振り向いた。 「それに………僕は、ソフィーが心配なんだよ」 そして、そのままハウルは扉の奥へと消えていった。 扉は自然と閉まり。 取手の色は黄色に変わる。 ソフィーは案の定赤い顔をしながら、扉の方をただただ見つめることしかできなかった。 「ハウル…………」 そして、ポツリとそう言葉を漏らしながら、ソフィーはふと先ほどのことを思い出していた。 そう。 私はね、ハウル。 ルーイのことが好きとか。 気になるとか。 そんなんじゃない。 そんなんじゃなくて、私はただ――――――――― 「ハウルのことが………心配なの」 そう。 ハウルの心臓を狙ってきたルーイ。 何かを企んでいるような目をしていたルーイ。 朝にカルシファーが言っていたことが、本当だったとしたら。 ルーイを、止めなきゃ。 今度は私が、ハウルを守らなきゃ。 ルーイのことが気になるんじゃなくって。 ハウルのことが―――――――――気になるの。 誰よりも。 何よりも。 かけがえのない、人だから。 大切な、人だから。 と、ソフィーはそこまで考えて、ふと手に何かの感触を覚えた。 見ると、手首に細い金色のチェーンが2重に巻かれていて。 そのチェーンには、指輪がついていた。 「………これ、ハウルの指輪?」 きっと先ほどハウルが知らずうちにソフィーの腕に巻きつけたのだろう、それは赤い宝石が2つついていて。 以前ハウルがくれた指輪は、過去の世界で砕けてしまったけれど。 これはきっと、もう一方のハウルが右手にしていた方の指輪だ。 ソフィーは、それをしばらく見つめてから腕から外し。 そっと自分の首にかけてみせた。 大丈夫。 私、ハウルを守ってみせる。 今度こそ、ハウルの力になってみせる。 そして、ソフィーは一人で何度か頷いたかと思うと、そのままどこへ行くのか取手は黄色のまま外へと飛び出した。 そんな様子をカルシファーはただただ暖炉から見つめていて。 「ハウル……お前の忠告、ちっともソフィーに届いてないぞ」 呆れた様に、小さくぼやいたのだった。 |