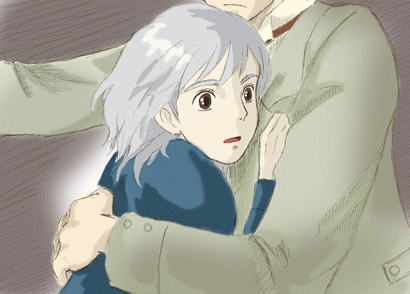 |
時間の呪文 −13− |
| ―――――――私、あなたにかかっている呪いを解きたいの! ソフィーは、本当に自然とその言葉が口から出ていたのだ。 すると。 その言葉を聞いた途端、ルーイが一瞬ピクリと身体を反応させた。 ソフィーの方へと視線を延ばして。 驚いたような表情を見せる。 「………ハウルさんに聞いたの?」 ソフィーはその言葉に、首を横に降ってみせる。 そして、ゆっくりと目を伏せる。 「違うわ、ハウルは聞いても何も教えてくれなかった」 するとルーイは、「ふぅん…」と呟いて。 視線を、彼女へと向けた。 目が、合う。 「ソフィーが?僕のために?」 僕だけの、ために? その言葉に、ソフィーは一瞬ぐっと詰まる。 ルーイのため。 もちろん、それもある。 それもあるけれど。 でも。 正直ハウルのためでもあって。 そこはやはり、恋する乙女である。 好きな人のことを守りたいという感情の方が、乙女が故に勝ってしまい。 でもでも。 大切な幼馴染みを助けたいという気持ちがあるのも事実で。 そう。 大切な、大事な幼馴染み。 いくじの無かった昔の私を、支えてくれた人。 〜〜〜〜〜〜って、そうじゃなくて! ソフィーは首を大きく横に打ち振った。 そして、頭の中の考えを一掃させる。 そう。 誰のためとか。 何のためとか。 そんなことよりも、今一番私がやらなくちゃいけないことは。 「ルーイ、あなたにかかってる呪いって……何?」 ソフィーは、ポツリと呟いた。 そうなのだ。 まずは呪いの種類。 それが分からなきゃ、何も始まらない。 すると、今まで黙ってソフィーの様子を見ていたルーイがクスクスと笑い出した。 まるで彼女の反応を、分かりきっていたかのように。 「ソフィー。さっき、ハウルさんは何も教えてくれなかったって言ったよね?」 その言葉に、ソフィーは頷く。 するとルーイは、ソフィーの方へと一歩近づいて。 薄く、笑う。 「ハウルさんは、教えてくれなかったんじゃない。教えられなかったんだ。呪いや契約っていうのは、そういうものなんだよ。人には教えられない、しゃべられないようになってる。自分で見抜かなきゃいけないのさ」 あ、と。 ソフィーは小さく声を上げた。 そういえば。 前に自分が90才の老婆になった時は、確かに呪いのことをしゃべることが出来なかった。 あのときは、カルシファーもハウルも私の呪いのことを知っていたけれど。 それは、決して自分からしゃべったものじゃない。 二人が、自分の力で見抜いたもの。 「………現に、以前ハウルさんにかかってただろう契約だって、ソフィーは自分で見抜けたのかい?」 自分で? ふと、考える。 あの場合、自分でっていうのだろうか。 カルシファーと契約を解く約束をして。 ハウルとカルシファーの行動を何気に見てたけど、分からなくて。 そのうち、マダムサリマンと謁見をすることになって。 戦火に巻き込まれて。 それで。 だから。 えっと。 ……………。 「み…っ見抜けたわ!」 たぶん、という言葉は、とりあえず飲み込んでおく。 しかしルーイは、眉一つ動かさずに。 「ソフィーには、無理だよ」 「そんなこと……!」 と、ソフィーはルーイの表情を見て言葉を詰まらせた。 冷たい、目。 まるで、自分の知っているルーイではないような印象すら受けて。 ソフィーは、息を呑む。 「……………」 と、そこでソフィーはふと我にかえる。 眉を、微かに潜めて。 ちょっと待って。 さっきは考えることが多すぎて、何となく聞き逃していたけれど。 ルーイは。 私に、何て言ったの? 『ハウルにかかってただろう契約』って言わなかった? ―――――――――!! 途端、ソフィーは弾かれたように顔を上げた。 そう。 やっぱりルーイは、ハウルの心臓のことを知っていたんだ。 そして今はもうその契約が切れて、ハウルの心臓が元に戻ったということも。 するとそんな彼女の様子に気がついたのか、ルーイが微かに目を細める。 自分を冷たく映す、黒の双眸。 瞬間。 ソフィーの背筋に、何か冷たいものが走った。 そのままゆっくりと、ベンチから立ち上がる。 「…………」 胸元の指輪が、微かに揺れて。 消え入るような声音で、言葉を紡ぐ。 「ルーイ……あなた、どうしてハウルを訪ねてきたの?」 風が出てきたのだろうか、ソフィーの銀色の髪をゆらゆらと揺らす。 でも決して、心地のいい風ではなくて。 微かに湿気を帯びた、不快な風。 「ルーイ、あなたの目的は何?ハウルに……何の用だったの?」 胸元の指輪を、ギュッと握る。 視線はルーイから、外さないまま。 するとルーイは、笑う。 先ほどとは違う、薄く冷たい笑みで。 「そうだね、強いて言うなら『助けて欲しかった』かな」 ―――――――欲しかった それはまるで、今の心臓を取り戻したハウルにはもう用が無い、と言わんばかりの返答で。 どきん。 どきん。 自分の心臓の音が、やけにうるさい。 ソフィーは、必死になってそれを抑えようとする。 「ソフィーは、昔からちっとも変わらないね。お人よしで、自分のことよりも他人のことを心配して」 頭の中に響いてくる、ルーイの声。 自分の知ってるルーイは、いつも優しくて。穏やかで。 いくじの無かった私を、支えてくれて。 「そして、誰よりも心がきれいで」 でも、いま目の前にいるルーイは。 昔とは、何かが違うような気がして。 「でも、それがときには……残酷だ」 不安に、なる。 ソフィーは、落ち着かない気持ちのままルーイを見上げた。 「ルーイ、何言って………」 するとそこには、先ほどまでとは違う自分を優しく見つめるルーイがいて。 まるで自分を愛しむような、目。 ソフィーはいいかげん訳がわからずに、それ以上言葉を続けることが出来ずに。 心持ち、わずかに後ずさりをする。 「僕は、君が………」 と、その時。 ソフィーの後ろを、大きな荷台を引く一台の馬車が通った。 彼女からは、死角の位置。 崩れた瓦礫を運んでいるのだろう、ガタガタと大きく音をならして。 そのちょうど、車輪の通り道。 大きな石が、転がっていて。 「…………!!」 ガタン! 瞬間。 ひときわ大きく、馬車が音を立てたかと思うと。 「ソフィっ!!」 突然ルーイが、大きく目を見開いてソフィーへと向かって駆け出した。 「え………?」 何が起きたか分からないソフィーは、ルーイの視線の先を追うかのように、後ろを振り向いた。 「……………!!」 ソフィーの目に飛び込んできたものは、車輪が石に乗り上げたのだろう、大きくバランスを崩して横に倒れこもうとしている馬車の荷台と。 自分に向かって落ちてくるだろう、大量の瓦礫の山。 近づいてくる瓦礫の山で、自分の顔が陰るのを感じる。 それはまるで、スローモーションの様で。 怪我だけじゃ、すまないかもしれない。 でも、突然のことすぎて頭が働かない。 足が、動かない。 間に合わない―――――――――!! ソフィーは、くるだろう衝撃に絶えようと固く目を閉じた。 と、その時。 「ソフィーっ!!」 「きゃっ!!」 突然ソフィーは腕を引っ張られたかと思うと、何かがかぶさってきた。 いや、抱き込まれたという表現の方が近いだろうか。 誰かなんて分かってる。 そう。 「ルーイっ!!」 そんな突然の状況の変化の中、ソフィーは自分を抱き込み庇ってくれているルーイの名前を叫びつつ、来るだろう衝撃に固く目を閉じた。 「―――――――――!!」 ……………。 ………………………。 しかし。 いつまでたっても、その衝撃はソフィーのもとへは届かずに。 その事実に、ソフィーは不思議に思いゆっくりと目を開けてみせた。 「あ…………」 すると。 ソフィーの目の前で、ルーイが右の手の平を、崩れてきた馬車と瓦礫に向かって真っ直ぐと伸ばしていたのだ。 斜めの状態で、馬車は倒れることなく停止し。 瓦礫は、宙に浮く。 そう。 ルーイの、魔法である。 ルーイが魔法で、崩れようとしていた馬車と瓦礫を止めているのである。 それは、はたから見たら重力というものを無視した、なんとも滑稽な図で。 ルーイは、右手をゆっくりと横に降った。 「………!」 すると、馬車は元の位置に戻り。 瓦礫は、荷台にガチャガチャと音を立てておさまる。 「あ…ありがとう、ルーイ」 まだ動揺が治まっていないのか、ソフィーは微かに震えた声で呟いた。 そしてルーイの顔を見ようと、視線を上に伸ばす。 そこには。 「ルーイ…?!顔色が悪いわ。具合悪いの?!」 「いや、何でもないよ」 先ほどよりも、真っ青な顔色。 微かに震えている、右手。 何でもないわけ、ない。 「ルー………」 ソフィーは、ルーイに詰め寄った。 ―――――――――!!! |
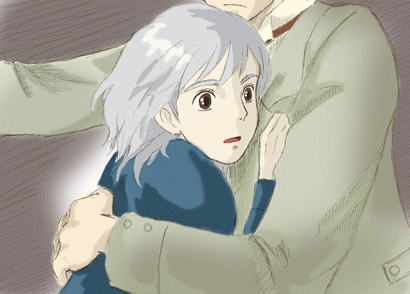 |
| 瞬間。 ソフィーは、言葉を失った。 頭の中が、真っ白になる。 「ルー………イ?」 詰め寄った時に、ルーイの胸元に置いた自分の手。 それはちょうど。 ひだり、側。 「ルーイ、あなた………」 背中に感じる、ルーイの手。 それは、ひんやりと冷たくて。 ゾクリと、鳥肌がたつ。 「あなた…………」 声が、震える。 ルーイの左胸に置いた自分の手が、震える。 そこから聞こえるはずの音。 感じなければいけない、動き。 伝わってこなければいけない、鼓動。 「心臓…………は?」 感じることの出来ない。 心臓の。 音。 |