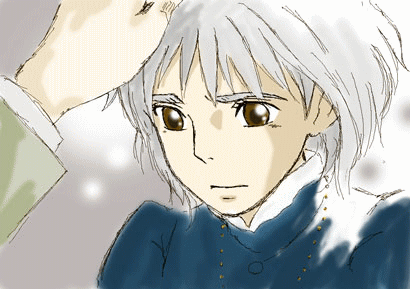 |
時間の呪文 −14− |
| 『はっきり言ってあいつの目は嫌いだね。まるで死んだような目をしてた』 以前、カルシファーが言っていた言葉。 ルーイのことを。 死んだような目をしてた、と。 あの時は、カルシファーが何を言っているのか分らなかったけれど。 今なら分かる。 きっと。 ううん、絶対。 ルーイも以前のハウルとカルシファーと同じように、契約を――――――― 「ルーイ…、心臓……どうして」 消え入りそうな声で、呟く。 するとルーイは、ふとソフィーから目をそらした。 かと思うと、今までソフィーに触れていた手をそっと離す。 「ソフィーには分らなくていいことだよ」 そんなルーイの小さな呟きに、ソフィーはズキリと胸が痛んだような気がした。 ソフィーには、僕は救えない。 関係ない。 そう、はっきりと言われたような気がして。 「ルー……」 苦し紛れもあってか、ソフィーは言葉を何とか紡ごうとした。 しかし、うまく言葉が続けられずに。 胸元の指輪が、そんなソフィーを急かすかのように、ゆらゆらと揺れる。 …………。 ………………。 しばらくの沈黙のあと。 はじめに口を開いたのは、ルーイだった。 まるで拉致があかないとでも思ったのだろうか、小さく吐息をついて。 冷たく、目を伏せる。 「……ソフィー。さっき言っていたよね。僕にかかってる呪いは何かって」 低い、声。 子供の頃とは違う「男の人」の、声。 「言ったよね。僕にかかっている呪いを、解きたいって」 それは、ソフィーの脳裏にやけに響いて。 「じゃあ、聞くけど」 目を、つぶりたくなる。 「………ソフィー、君は本当に僕を救えるの?」 本当に、救ってくれるの? そう言って、ルーイは自虐的とも取れる笑みを小さく浮かべた。 「……………」 一瞬、返答に詰まる。 呪いを解く? ルーイを救う? 前に、ハウルの心臓を私が戻した時のように? ほんの数秒の間に、ソフィーの頭の中では過去の記憶がグルグルと回っていた。 どうやったっけ? どんな風にやるんだっけ? カルシファーに想いを込めて。 ハウルの心臓に手をあてて。 えっと。 だから。 ……………。 「と……解けるわ!」 色々と考えて。 何とかなるだろうという結果にたどりついたのか、ソフィーは少々上ずった声で返答した。 しかし。 そんなソフィーとは裏腹に、ルーイは「ふぅん」と眉を潜めて。 クスクスと、笑い出した。 「解くって?呪いを解いて、僕の心臓をもとに戻すってことかい?」 そして、ルーイは自分の左胸に手をあてた。 何の音もしない、からっぽの身体。 「やっぱりソフィーには、本当の意味で僕は救えない」 「どうして…っ」 思わず、声を上げる。 それもそのはず。 ソフィーにとったら、先ほどの言葉は、ちょっとした一大決心だったのだ。 どうやったら呪いが解けるのか。 どんな条件がそろえば出来るのか。 本当にあの時は無我夢中だったものだから、はっきり言って方法なんてさっぱりなのだ。 それに、前回は相手が「ハウル」だったのだ。 大好きな、ハウルだから。 想いも感情も全部ひっくるめて、心から守りたいと思ったハウルだから。 だから。 根拠もなにもないけれど、呪いを解くことが出来たような気がするのだ。 しかし。 相手がルーイとなると、話は別である。 そしてそれが、理屈でどうにかなるものでも無いから尚更に。 だからこそ、先ほどの質問に答えるのには、それなりの覚悟が必要だったわけで。 それなのに。 するとルーイは、そんなソフィーを横目に静かに息を吐いた。 風が出てきたのだろう、ルーイの髪を静かに揺らして。 「……ソフィー。どうやってハウルさんの呪いを解いたのかは分からないけど、正直僕は自分の呪いの解き方なんかには興味はないんだ」 呪いなんて、解けなくてもいいんだ。 ―――――――――。 一瞬。 本当に一瞬だが、ソフィーはルーイが何を言っているのか分からなかった。 言葉の意図が、分からなかったのだ。 「何を…言ってるの?」 何とかごちゃごちゃになった頭を動かして、先ほどの言葉の数々を思い起こしてみる。 本当の意味で? ルーイを救う? 自分の呪いの解き方には、興味がない? 呪いを解く=ルーイを救う、ではないのか。 「……ソフィーには、無理だよ」 頭の中で、答えの糸口が見つからないまま。 そんなソフィーに、ガツンと。 確信をつかれたかのような、そんな音。 役立たず。 まるで、そう言われているような気さえしてきて。 「そんなこと……っ」 そんなルーイの言葉を否定しようと口を開くが。 なぜだろう。 この後の言葉が、続かない。 言葉が、出てこない。 「……………」 するとルーイは静かに目をふせて。 そのまま、ソフィーの頭に左手をのせた。 かと思うと優しく、本当に優しく頭をなで始めた。 まるで壊れ物に触るかのように、ゆっくりと。 ―――――――――。 もう、何がなんだかさっぱり分からない。 ルーイが何を考えているのか。 自分が、何をすればいいのか。 しかし。 そんなルーイの手は、昔のことを思い出させるかのように。 小さかった意気地なしのソフィーと。 そんな彼女を優しく助けてくれた、小さなルーイ。 昔の、二人。 昔の、まんま。 それは何も変わらずに。 唯一変わったことといえば、ルーイの手の平の冷たさと、時折見せる悲しげな黒の双眸くらいか。 その双眸は、時には氷のように冷たくさえ感じて。 「……………」 じわり、と。 何故かソフィーは、突然目に涙が浮かんできたのを感じた。 悲しいのか、寂しいのか。 何も出来ない自分が悔しいのか。 理由なんて、自分でもさっぱり分からない。 分からないのに、じわじわと視界が歪んでくるのだ。 うぅ〜〜〜………。 ソフィーは涙がこぼれないように、何とか耐えてみせた。 ぐぐっと、拳を強く握って。 |
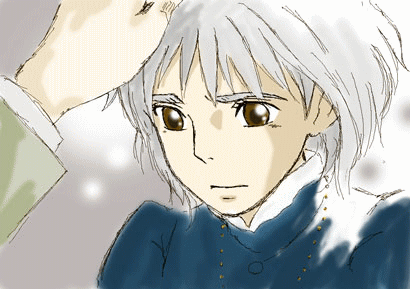 |
| そう。 泣くわけにはいかないのだ。 ここで泣いたら、自分が本当にただの役立たずのように思えてきたのだ。 頭に感じる、ひんやりとしたルーイの手。 それはまるで、血が通っていないような錯覚を起こさせるほどで。 「………私、助けたい。ルーイの手に、昔と同じ温かさを取り戻したい」 だから。 そんなソフィーの言葉に、ルーイは微かに目を細めて。 音も無く、息を吐く。 「……ソフィー。僕はもう、昔の僕じゃない。悪魔に心を売ってしまったから。だから……」 頭を撫でていた手が、止まる。 「だから、人の心は、もう持ち合わせてはいないんだよ」 「そんなこと……っ」 しかし。 そんなソフィーに言葉を遮るかのように、頭の上にあるルーイの左手に少し力が入り。 そのまま、ルーイはゆっくりと目を閉じた。 「………やっぱり君は、残酷だ」 そして、微笑む。 苦しそうに、それでいて愛しそうに。 そしてそのまま、踵を返した。 ソフィーの頭から、音もなくルーイの手が離れて。 そのまま、ソフィーに背中を向けゆっくりと歩き出す。 「ルーイ!」 叫ぶが、ルーイは歩みを止めようとはせずに。 振り返る、仕草もみせない。 「……じゃあ、どうして助けたの?」 姿が、次第に遠くなり。 歩く音も、遠くなる。 「どうしてさっき、私を助けてくれたの?」 遠く。 遠く。 「それは…あなたが……」 風の音だけは、近く。 「あなたが……まだ人の心を持っているからじゃないの……っ?」 その時、微かにだがルーイの背中が反応したように見えたのは気のせいだろうか。 しかしソフィーの方は、一度も振り返ることはなく。 「ルーイ……!!」 そんなルーイの背中を見ながら、ソフィーはただただ両手を強く握り締めることしか出来なかったのだ。 空はいつしか雲がかかって。 太陽の光を、遮る。 まるで、ソフィーの心に影を落とすかのように。 |