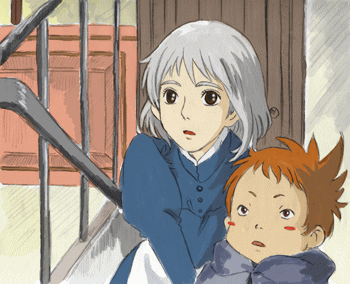 |
時の呪文 −4− |
| 一方その頃。 城の中では、ハウルとルーイの二人が視線を合わせていた。 カルシファーは黙ったまま薪の間に隠れており、一件普通の暖炉の火に見える。 「お久しぶりです、ハウルさん。探しましたよ!」 「ルーイ……」 ルーイと呼ばれたその青年は、少々驚きの表情を見せているハウルに、あどけなく笑ってみせた。 そして入り口にある何段かの段差を上りきり、部屋の中へと足を踏み入れた。 ハウルはそんなルーイを特に止める様子もなく、椅子に座ったまま黙っていて。 目が、合う。 しばらくの沈黙が流れて。 「……………」 ハウルは無意識に、過去の記憶を思い返していた。 そんなハウルの記憶の中で、この青年が登場するのは魔法学校時代。 そう。 この青年は、ハウルが魔法学校に通っていた時の後輩にあたる。 はっきりいって、あまり出来はよくなかったような気がするが、持ち前の明るさが手伝ってか何かと学校では目立っていた気がする。 しかし、ハウル自身学生時代に、誰かと馴れ合うことはあまりなくて。 ルーイとも、数える程度しか話をしなかったような気がする。 それなのに。 その後輩が、いまさら自分に何の用だというのか。 ハウルは、椅子に座ったまま目線だけを僅かに動かした。 そして、小さく息を吸う。 「……で、君の用件は何?」 そのまま、それだけを言葉にする。 基本的にハウルは、心を許していない相手にはクールそのもので。 正直「冷たい」と感じることもあるだろう。 しかし、ルーイはそんなハウルに動じる様子もなく、話を続け始めた。 「実は僕、つい最近まで王宮で働いていたんです。サリマン先生のもと」 「…………」 まぁ、当然のことだろう。 ハウルは、静かに目を細めて見せた。 学校を卒業するときに、結ばされる契約。 それに基づく、契約書。 それがある限り、卒業生にとっての王宮の命令は絶対。 そしてそれに逆らった者は、王宮から狙われることとなる。 以前の、自分のように。 そして、ルーイも例外になく、その契約書のもと働かされていた手口だろう。 ―――――――――戦争の道具として。 と、その時。 ふとハウルは、ルーイの言葉に気になる部分があり復唱してみせる。 「働いて…いた?」 そう。 「いた」は過去形である。 と、いうことは。 「ええ、辞めたんです。戦争が終わるちょっと前に」 そう言ってルーイは、再び笑ってみせた。 そして次々と言葉を並べ始める。 「ちょっと考えるところがあって。それに、もともと僕は戦争にはあまり賛同してはいなかったんです。それで戦争に出るのが嫌になって辞めちゃったんです」 ハウルは、そんなルーイの話を無言で聞いていて。 するとルーイは、一瞬だが目を伏せる。 そして、今度は切れ切れに言葉を紡ぎ始めた。 「辞めるというよりは……逃げるって方が言い方が正しいかもしれません。戦争から逃げるということは、契約書の誓いを破ったも同然なのですから」 そして、苦笑いをしてみせた。 深い茶の髪の毛を、微かにゆらして。 「……でも、辞めてもハウルさんみたいに王宮から狙われることは無かったです。僕程度の魔力は、あまり王宮にとっては必要なかったってことなんでしょうね、嬉しいんだか複雑なんだか…」 その言葉に、ハウルは僅かにだが反応する。 一瞬だが、眉を潜めて。 そして、ゆっくりと溜息をついた。 少しの間をおいて。 「……それで?もう一度聞くけど君の用件は何?」 ハウルの落ち着いた、それでいて鋭い声音にルーイは再びハウルを見た。 そして、俯く。 「僕は………」 ルーイは、それだけを呟くと暖炉の方へと近づいた。 パチパチとカルシファーの燃える音が響く。 そのままルーイは、暖炉で灯る暖かな火へと視線を落とし黒の双眸を細めた。 横顔が、穏やかな火の光で僅かに照らされて。 「……サリマン先生がよく言ってました。ハウルさんは、まれに無いと言っていいほどの魔力の持ち主だと」 視線は、暖炉の火から離さないまま。 息を、ゆっくりと吸って。 「そして………」 と、その時。 「ただいまーーっ!」 マルクルの元気な声と同時に、入り口の扉が勢いよく開かれた。 続いて、大きなカゴを持ったマルクルとソフィーが、部屋の中へと入ってくる。 「ただいま、ハウル。……って、あらお客様?」 ソフィーは、すぐに部屋の中に見慣れない人物がいることに気がつき、そう言葉にする。 その声に、ルーイはゆっくりと振り向き。 ソフィーへと、目を向ける。 二人の視線が―――――――――合う。 「…………ソフィー?!」 「え……?」 |
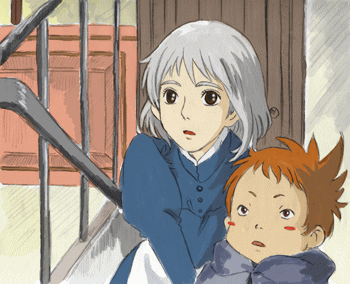 |
| ソフィーを見て驚愕した表情のルーイと。 突然自分の名前を呼ばれて、ただただルーイを見つめることしか出来ないソフィー。 部屋の中は、一気に妙な空気に包まれたのだった。 |