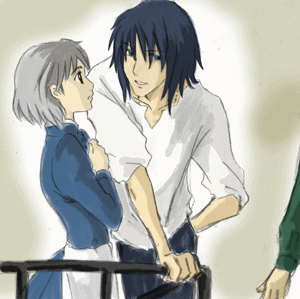 |
時の呪文 −5− |
| 「ソフィー?……本当にソフィー?」 ルーイは、驚いた表情をしたままソフィーに近づいた。 そして一歩手前まで来て、ソフィーの顔をしばらく見つめたかと思うと、懐かしそうに目を細めてみせた。 「やっぱりソフィーだ」 そして、本当に嬉しそうに笑う。 「え?……え?」 訳が分からないのはソフィーである。 思わず胸の前で拳を固く握って、後ずさりをする。 そして、ルーイの顔をじっと見た。 「……………」 少し細めの、自分より僅かに高い身長。 深い、茶色の髪の毛。 黒の、双眸。 「あ………っ」 ソフィーは、今の今まで消えかけていた昔の記憶が、一気に頭の中で弾けたのを感じた。 と同時に、この青年の昔の面影も、記憶の中で鮮明に蘇り始める。 そう。 私、知ってる。 この笑顔。 この、雰囲気。 これは。 「ルーイ……っ?!」 遠い―――――――――昔の記憶。 一方ハウルは。 暖炉の椅子に座りながら、ただ無言で二人を見ていることしか出来なかった。 ソフィーを見て、驚き喜んでいるルーイと。 今だ信じられないといった表情をしているソフィー。 そしてソフィーがルーイに向けて、笑う。 懐かしそうに。 嬉しそうに。 そして、そんな表情を見せているソフィーを見て、ハウルは無意識に自分の目尻が上がっていくのを感じた。 今まで生きてきた中で、感じたことが無いほどの、この感情。 この苛立ち。 ハウルは、音もたてずに椅子から立ち上がると、入口の所で話し込んでいるソフィーとルーイの方へと足を向けた。 静かに、それでいて歩巾は大きく踏み出して。 二人の所まで、来る。 次の瞬間。 ハウルは、入り口の段差に付いている鉄柵に、二人の間を割って入るかのように手をかけた。 ソフィーとルーイ。そしてその間にハウル。 |
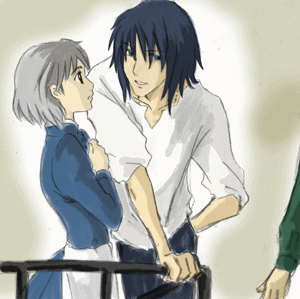 |
| 「ハっハウル?!」 あまりに突然のことに驚いたのか、ソフィーが小さく声を上げた。 しかし、今はあえて無視をする。 そしてそのままルーイの方へと視線を伸ばした。 「……で?いいかげん君の用件は何?」 そう言葉にしながら、ハウルは青の双眸にルーイを映す。 口では微笑んでいるものの、目は冷たく鋭いもので。 一瞬、ルーイが息を呑むのが分かった。 しかし。 すぐにルーイは、いつもの様に明るく笑って。 一歩、下がる。 「いえ、今日はいいです。また日を改めてお伺いします。……でもソフィー、本当に驚いたよ。どうして君がハウルさんの家に?」 思いがけず、突然核心をつかれたソフィーは、一瞬言葉に詰まる。 そして、みるみるうちに顔を赤く染めだしたかと思うと顔を俯かせた。 「あ、うん……。その……えっと……」 そんな態度をみせるソフィーに、ルーイは何かを感じ取ったのか「あぁ」と口にしてみせた。 そして、微笑んでみせる。 「そっかぁ」 何が「そっかぁ」なのか分からないが、とりあえずソフィーは顔を赤くしながら頷いて見せた。 そしてルーイに、ぎこちなく笑い返す。 するとルーイは、ハウルとソフィーの横を通り過ぎて入り口の扉へと向かった。 そのまま取手に、手をかける。 くるり、と振り向いてこちら側を見て。 「また来ます。ハウルさんお話はその時に。………それとソフィー」 「え?」 ハウルの横で、そう聞き返してくるソフィーを見ながら、ルーイは再び目を細めて見せた。 どこか懐かしそうに、小さく呟く。 「髪、染めたんだね。前の赤錆色、きれいだったのに……」 その言葉に、ソフィーは一瞬言葉をつまらせて。 対するハウルは、微かにだが睨むような視線を向ける。 「…………」 すると、しばらく黙っていたソフィーが、一度深呼吸をした。 そして、柔らかな表情で呟く。 「……うん。でもね、私は今の髪の色の方が好きなの」 そう言いながら、本当に穏やかな表情をして。 そんな表情のソフィーを見て、ルーイは「そう」と呟いた。 そして、今度こそ扉の取手をひねりドアを開ける。 ドアの隙間から、外の眩しい日の光が差し込んで。 「それじゃあ、今日は失礼します。またね、ソフィー」 そう言って、ルーイは外へと出て行った。 扉の閉まる音が、部屋の中に異常に大きく響いて。 部屋の中が、シンと静まりかえる。 しかし、とりあえずは。 一難去ったのを確認したのか、まず大きな溜息をついたのはハウルでもソフィーでもなく。 この一部始終を始めから見ていた、カルシファーだったのだ。 |